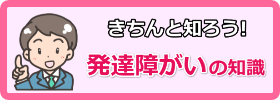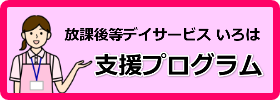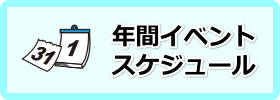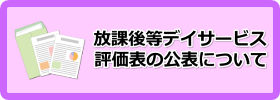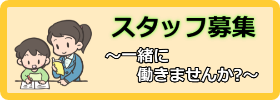トゥレット症候群
症状
トゥレット症候群におけるチックとは、突発的で急速な、反復性がある、リズムなくくりかえされる運動、または発声のことを指します。
4〜11歳頃に発症することが多く、もっとも発症しやすいのは6、7歳。女子よりも男子に多く発症がみられるのも特徴です。チック症の症状は慢性化する場合もありますが、ほとんどが一過性で、年齢を重ねるにつれてチック症が改善するといわれています。
チック症の症状は、大きく「運動性チック」と「音声チック」に分けられ、それぞれに「単純チック」と「複雑チック」があります。
運動チック
●単純性運動性チック
まばたき、首振り、顔をしかめるなどがあります。
●複雑性運動チック
物に触る、物を蹴る、飛び上がるなどがあります。
手にチック症状が現れた場合は、文字を書くのが難しくなるなど、日常に支障をきたすこともあります。
音声チック
●単純性音声チック
発声、咳払い、鼻鳴らしなどがあります。
●複雑性音声チック
一般的に人前や公共の場でいうことではない汚言症、他人の言った言葉をくりかえす反響言語や、音声や単語の発声をくりかえす反復言語などがあります。
この「運動チック」と「音声チック」の両方が(同じ時期とは限らず)存在し、一過性ではなく1年以上慢性的に続くのがトゥレット症候群といわれます。
そして、トゥレット症候群にはしばしば合併症がみられます。
合併症として多いものには以下のものがあります。
強迫性障がい
不安障害のひとつで、不合理であると理解している考えやイメージが自分の意に反してくりかえし浮かび、不安や恐怖を感じます。そして、その不安や恐怖を和らげる行為をくりかえし行ってしまう障がいです。
注意欠陥・多動性障がい(ADHD)
発達障がいのひとつで、年齢に見合わない不注意さや多動性、衝動性が原因で日常に支障をきたす状態のことを指します。具体的な行動としては、思いついたことを深く考えず行動に移してしまう、好きなこと以外には関心を示さない、などがあげられます。
学習障がい(LD)
知的発達の遅延や身体的な障がいはないものの、読む、書く、計算するなどの学習知識のいずれかが低く、学習に困難を示す子どもの状態を指します。
不登校
心になんらかの葛藤を抱えているために、登校ができない子どものことを指します。
これらの子どもは、自らが動く力や、周囲と関係を構築していく力がやや低い傾向にあります。
中でも、小児期には注意欠陥・多動性障害が、10歳以降には強迫性障がいが、合併症として多く見られます。
上記以外にも、衝動性・攻撃性の高まり、自傷・他害行為、睡眠障がい、二足歩行が上手に行えないなどの障がいが見られることもあります。
原因と対策
原因は完全には解明できていませんが、トゥレット症候群の65~90%に家系発症がみられることから、遺伝的要因があると考えられています。
また、一卵性双生児の場合、一致率が53%と顕著に高く、二卵性双生児の場合は8%というデータも報告されています。
さらに、原因として、大脳基底核のドーパミン神経受容体の異常が示唆されています。
ドーパミン神経とは情動、注意、意欲、報償、依存、歩行運動などをつかさどる重要な神経です。
このドーパミン神経系の活性低下にともなう受容体の過活動が、トゥレット症候群を引き起こすと考えられています。
治療方法としては、心理療法と行動療法が用いられます。
中でも有効なのが、行動療法の一つ「習慣逆転法(ハビットリバーサル法)」です。
習慣逆転法(ハビットリバーサル法)とは、意識化練習、拮抗反応の学習、リラクゼーション練習、偶然性の管理、汎化練習の5つのステップを用いた治療法で、この5つのステップをマスターすることで症状が大きく改善するとされています。
また、日常生活に支障をおよぼすほど重症な場合に限り薬物療法が行われます。
用いられる薬には、ドーパミンの過剰な働きを抑制する「ハロペリドール」などがあります。
トゥレット症候群の確かな治療方法は確立されていませんが、症状の早期診断、年齢に応じた環境の調整、疾患に対する本人と周囲の理解が大切です。